創業融資とは?
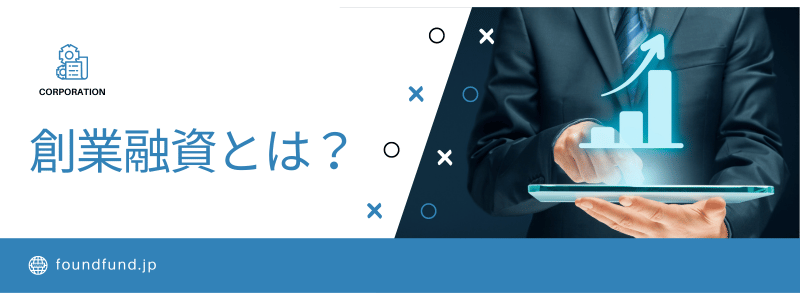
創業融資とは、新たにビジネスを始める起業家が資金を調達するために利用する融資のことです。
起業初期段階で必要となる運転資金や設備投資のための資金を、金融機関から借り入れる手段を指します。
創業前や創業したばかりのときは、事業の実績もなく売上も未知の状態のため融資を受けるのは難しいといわれています。
事業主の方が申し込める融資には、公的機関や金融機関の創業融資や、ビジネスローン、さらにソーシャルレンディングなどがあります。
この記事では、創業融資の基礎知識から、難しいと言われる創業融資を受けるためのポイント、資金調達方法として有効なビジネスローンまで解説していきます。
個人の方が融資を受ける場合には消費者金融の審査に落ちる理由とその対策を頭に入れておきましょう
創業融資を受けるメリット

創業融資を受けるメリットには大きく分けて、3つのものがあります。
創業融資を利用できるのは、新しく事業を始めようとする方や、起業後数年の若い企業です。有利な条件で利用できる創業融資が多いため、メリットを知ってぜひ利用しましょう。
資金調達の手段を増やせる
資金調達の手段を多くできるかどうかは、事業をする方にとってこの上なく重要な点になります。
運転資金を調達することを資金調達とよび、3つの方法があります。
- 負債(仕入れ債務や借入など)を増やす
- 資本を増やす(増資、黒字経営)
- 保有資産の現金化
このうちの、負債を増やす資金調達法には「公的融資」「銀行融資」「ビジネスローン」等があり、審査を伴いますから必ず融資を受けられる保証はありません。
融資はスピーディーで審査も甘い傾向にあっても金利が高いローンや、審査日数や条件は厳しいけれど金利は低いローンなど各種融資には特徴があります。
資金が必要な緊急度、金額、繰り返し利用する可能性があるのかに応じて、資金調達の方法を選んでいきましょう。
また適切な調達方法の手段が多いほど、レバレッジ効果が期待できます。レバレッジとは借入が多くなると、より大きな利益を生み出せる可能性があることです。
創業融資を利用すると、融資の手段を増やせるメリットとなるでしょう。
返済条件が有利なものが多くある
創業融資では返済条件が、融資を受ける側にとって有利なものが多い特徴を持っています。
たとえば、日本政策金融公庫で創業時に利用できる「女性、若者/シニア起業家支援資金」なら、設備資金は20年以内、運転資金は7年以内の返済期間です。
また、元金の返済を2年延長できるため、事業が軌道に乗ってからの返済も可能になるでしょう。
金利は1%台から2%台のものが中心で、負担も少なくなっています。
返済の条件が良い融資を選んでおくと、事業にも良い影響を及ぼします。
事業計画のブラッシュアップが求められる
創業融資では、事業計画書を提出しますが、審査を通過するためにブラッシュアップが求められます。
事業計画書を作成すると、事業のプランを明確に頭の中で組み立てられますし、目標がさらにはっきりとするでしょう。
今後どのように行動するかの道筋をつけるためにも、事業計画書は大切です。
さらに自分で事業計画書を作成したうえでさらに、創業融資を受けるために信頼できる事業であり、将来性もあると理解してもらえるためのブラッシュアップも必要になってきます。
熟考して作成した事業計画書は、事業を進めていく拠り所になります。
3つのメリットを活かし、事業のスタートアップフェーズを成功に導くための戦略を練っていきましょう。
創業融資は大きくわけて5種類のものがある

創業融資にはその特徴によって、大きく分けると5種類あります。
創業者を対象に支援している制度が創業融資ですが、借入先等により分類すると分かりやすいでしょう。
- 日本政策金融公庫の融資
- 地方自治体による制度融資
- 信用保証協会の保証付き民間金融機関による融資
- ビジネスローン
- 融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
それぞれの特徴を理解しておくと、自分の事業により適切な融資を選べ、確実な資金調達への第一歩とできるでしょう。
日本政策金融公庫による融資は創業資金借入先の第一歩
民間金融機関の取り組みを補完する目的をもつ日本政策金融公庫は、政府系金融機関に分類されます。
創業前の方や、事業を始めて間もない中小企業や個人事業主などの方にとっては最初に融資を検討したい借入先といえます。
融資限度額の大きさや金利の低さから、利用しやすい融資といってよいでしょう。
代表的な創業時支援の融資制度
新規開業資金・生活衛生新企業育成資金・新創業融資制度・資本性ローン など
地方自治体による制度融資は長期安定した資金調達方法
地方自治体による制度融資とは、地方自治体・金融機関・信用保証協会の三者が連携して融資を行う制度融資です。
地方自治体が信用保証協会と協調することで、中小企業が金融機関から融資を受けやすくなります。
自治体が面接を行って、金融機関に紹介状(推薦状)を発行する方式のものが多く、長期で安定した資金調達が可能な制度です。
地方自治体により融資制度に違いがあるため、必ず申し込む自治体の制度を確認してください。
信用保証協会の保証付き民間金融機関による融資は事業開始前に最適
民間の金融機関で受ける融資ですが、信用保証協会の保証がつくものです。
保証付融資とよく聞くのは、このタイプの融資となります。
信用保証協会の保証があるので、原則として保証人や担保が不要で利用できるので、これから事業をする方にとっても申し込みやすいでしょう。
また、金融機関は貸し倒れのリスクを防げるので、積極的に融資を行いますから審査に通りやすい傾向があります。
ビジネスローンは審査期間が短く緊急時に便利
ビジネスローンは事業者ローンとも呼ばれ、自営業者や法人経営者が利用できるローン商品です。
審査期間が短く、保証人や担保がなくても借りられるため、事業主の方がすぐお金が必要なときにも対応しやすい特徴を持っています。
その一方で、金利が他の創業融資に比較すると高く、返済計画を立てないとかなり高額な利息を支払う必要が出てきてしまうでしょう。
ただし経営年数1年以上等の申込条件が定められたビジネスローンもあるので、創業融資として利用できない場合もあります。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は利用の条件を確認しよう
融資型クラウドファンディングは、個人投資家から集めた少額の資金をファンドを通じて大口化した後、資金が必要な企業に貸し付けるものです。
ソーシャルレンディングとも呼ばれている仕組みで、必ずクラウドファンディング業者が介在する融資となります。
創業する方が資金調達に使いやすそうと感じるかもしれませんが、担保が必要な場合があったり、金利が高かったりするケースも多く、起業時には実はあまり向いていません。
創業融資の申し込み方法

創業融資に申し込む場合には、手続きから審査の流れ、提出するために準備しておく書類を把握しておきましょう。
ここでは、創業時に最も利用する方が多いと考えられる、日本政策金融公庫での申し込みの流れをご紹介します。
日本政策金融公庫はまず相談から
申し込みの流れ
- 相談(電話で問い合わせ。オンラインや支店窓口での相談は要予約)
- 申し込み(インターネットで24時間申し込み可能)
- 面談(事業計画について面談。店舗や工場への訪問あり)
- 審査(事業計画等をトータルで審査)
- 契約(審査通過後融資決定なら契約)
- 融資実行(希望した口座への振込)
日本政策金融公庫への申し込みの流れは、相談からスタートします。
日本政策金融公庫は、創業や事業拡大を目指す個人や法人を対象に、幅広い融資オプションを提供しています。
低利の融資条件や、初心者向けの相談窓口など、起業家にとって有益なサポートが充実しているのが特徴です。
日本政策金融公庫は、申し込み前にオンラインや支店窓口で相談を行います。
融資の制度や、手続きの問い合わせは電話0120-154-505でも受け付けていますので、都合に応じて利用するとよいでしょう。
相談後、融資を希望するならインターネットで申し込みます。
申し込み時に必要な書類は、創業計画書、設備資金なら見積書、履歴事項全部正永所または登記簿謄本などです。
利用する融資等により提出書類は異なるため、相談時にきちんと確認しておきましょう。
申し込み後、面談で詳細を伝えたあとに融資が可能と判断されれば、創業資金を借りられる状態になります。
融資決定判断後に契約手続きをし、希望する口座へ振込による融資となります。
計画的に資金計画を立て、確実な返済計画を提示することが、日本政策金融公庫での融資獲得の鍵となります。
創業融資の審査基準となるポイント4つ

創業融資を受けるためには、金融機関の審査を通過する必要があります。
審査を通過するために、各創業融資では審査基準を設けています。ただし、審査基準は非公表ですから、審査でどの点を重視されるのかを知っておくと良いでしょう。
具体的なポイントを4つ、解説していきます。
自己資金がどれくらい準備できているか
創業するにあたって、どれくらい自己資金を準備できるのかは、最も重要なポイントと言ってよいでしょう。
自己資金割合といって、創業資金のうち何割自己資金を準備したかが審査通過を左右します。
それではいったい何割なら審査に通るのかは、もちろん明確には各創業資金を取り扱う公庫や金融機関は公表していません。
しかし一般的には、自己資金は借りたい額の半分から3分の1は持っておかないと審査通過が難しいといわれています。
特に創業融資は経営の状態等でアピールできませんから、自己資金を準備するしかない部分があるのです。
個人信用情報の確認でローン利用状況をチェック
信用情報は、融資の審査におけるもう一つの重要な要素です。過去の借入れ履歴や返済状況などがチェックされ、それに基づいて起業家の信用度が評価されます。
個人的なローンの利用履歴も、融資を受けるからには影響するわけですね。
自分の信用情報を把握し、延滞履歴が残っていないかなどをチェックしておきましょう。
さらに、自己資金準備をどのように行ったかを把握する際に通帳の確認が行われます。
預金通帳で、手持ち資金をどのように貯めていったのかを審査時に把握する必要があるためです。
たとえば、お給料からコツコツ貯めたのではなく、突然どこかから振込によってまとまった金額が入っていたら自己資金とはみなされません。
創業する事業での経験や能力
創業融資では、これまでの経営状況は提出できない分、起業する方の経験や能力を審査材料とします。
これから経営していくビジネスに関して、どれくらいの経験を持っていて、どんな能力がアピールできるのかが審査で大切なポイントとなるのです。
今までお花屋さんでアルバイトしていた方が、「IT事業を始めます」といっても審査では不利になってしまいます。
もちろんまったく新たな分野で創業してはいけないわけではないのですが、どんな点を自分の能力として伝えられなければ、審査には通りません。
返済の可能性は十分か
審査を行い、ビジネスとして利益が上がらないと判断されれば、返済できないという見込みになるため審査否決となります。
どれほど事業に熱意をもっていても、売上が上がらなければ、お金を貸す側は返済能力がないと判断するしかなく貸付はできません。
実際にはこれから創業する場合には、事業計画書とその妥当性が審査での重要なポイントになっていきます。
事業計画書の利益の推移に説得力はあるか、きちんと説明でき説得力があるかを検討しないといけないのです。
創業融資で採用されている主な返済方式

創業融資を受けた後は、返済計画に従って貸し付けた資金を返済していく必要があります。
返済方式と呼ばれる返済額の計算方法に基づいて、返済していきます。
適当な額を適宜返済していくのではなく、毎月融資受けた額に基づいて返済していくのです。
返済方式には、元本均等返済と元利均等返済の二つが主にあります。創業融資により採用されている返済方式が異なっていることもあります。
それぞれの返済方式の特徴を知っておくと、融資先選びの際に参考になるでしょう。
元本均等返済は返済当初の返済額が高め
元本均等返済は、借入れた元本(=元金)を一定期間にわたって均等に分割して返済し、利息を借入れ残高に応じて支払う方法です。
元本均等返済方式では、初期には月々の返済額は高めですが、段階的に返済額が減少していきます。そのため、将来的な資金計画を立てやすい特徴があります。
元利均等返済は月々の返済額は一定
元利均等返済は、元本と利息を合わせた総返済額を一定の期間で均等に分割して返済する方法です。
元利均等返済方式では、毎月の返済額が一定なので資金管理がしやすいというメリットがあります。
ただし、元金と利息の合計が返済額ですから返済当初は利息額の割合が大きく、なかなか借りた元金が減っていきません。
また約定返済となる毎月の返済額のみ返済していると、返済期間が長期になってしまい、最終的に支払う利息額が大きな額となることもあります。
事業の収益性やキャッシュフローの状況を考慮して、適切な返済計画を立てておくこと、返済シミュレーションをきちんと行うことが重要です。
創業融資を受けるためのポイント

創業融資を受けるためには、事業計画書の作成、信用情報の確認などのポイントを押さえる必要があります。
特に事業の実績でアピールできない創業融資では、事業計画書は大変重要な位置を占めています。
しっかりと準備してから、金融機関への申し込みを行うと、融資審査の通過率を高めることができます。
適切な事業計画書の作成
事業計画書は、創業融資を受けるための最も重要な書類の一つです。
事業計画書には、企業や事業の概要、コンセプト、従業員の状況、競合分析や市場規模、販売戦略やビジネスモデル、収益予測などを書きます。
事業の成功を左右する要素を包括的に記述し、申込先に提出します。
特にまだ事業がスタートしていない創業融資では、具体的で実現可能な事業計画を作成することが、融資獲得のカギとなります。
信用情報の確認をしておく
信用情報は、個人の過去の金融取引履歴を示すもので、融資の審査において重要な要素を成すものです。
延滞履歴や、債務整理の履歴があると通常審査には通過しません。
過去に延滞したり、返済しなかったりした人物はまた繰り返すと判断されてしまうからです。
さらに複数のローンに短期間で一度に申し込んでいる場合にも、審査には不利です。
多数のローンに申し込んでいるとお金に大変困っていて、返済能力を超えた申し込みをしている、多重債務に陥るおそれがあると疑われることによります。
信用情報を事前にチェックし、誤情報があれば修正を依頼する、ローン利用件数が多ければまとめたり、低い残高のものは返済してしまうなどで対策しましょう。
信用度を改善し、返済能力が十分にあることを審査でわかってもらうことが重要です。
担保や保証人の準備
担保や保証人が必要ない創業融資もたくさんあります。
しかし、保証人や担保を用意できれば、融資の条件を改善できるローンも見つかるでしょう。
不動産や設備など、価値のある資産を担保として提供できる場合は、融資の審査において有利に働くことがあります。
担保にできる資産の範囲や評価について、事前に情報を収集し、融資へ申し込む前に準備しておくことが望ましいです。
また、ぎりぎり審査に通過するかどうか難しいけれど、保証人を立てれば審査可決の可能性が高まる場合もあります。
保証人が必要になった場合にどうするかを考えておくと、審査がスムーズに進むでしょう。
ビジネスローンとは事業資金専用のローン
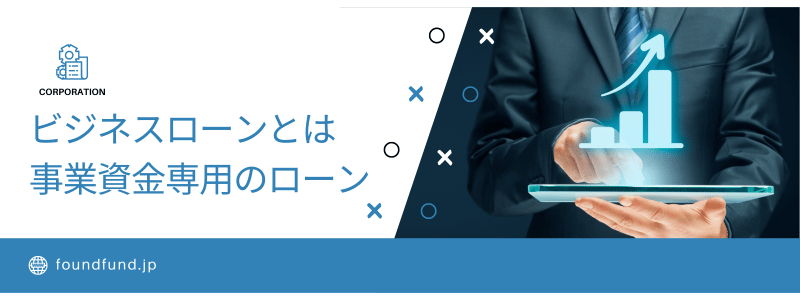
ビジネスローンとは、企業が事業資金を調達するために金融機関から受ける融資のことです。
金融機関と一口にいっても、ビジネスローンを取り扱っているのは銀行、信販会社、クレジットカード会社、消費者金融など様々です。
それぞれ金利、限度額、保証人や担保が必要かどうかなどの特徴は異なります。
また、ビジネスローンは運転資金の調達や設備投資、事業拡大など、さまざまな目的で利用されます。
ビジネスローンの基本から種類、審査基準、そしてメリット・デメリット等をまとめました。
ビジネスローンの種類を金融機関で分類
ビジネスローンは、金融機関、利用者のお金の使いみち、利用条件によって、申し込み者に最適なものは異なります。
ビジネスローンを分類する際には、金融機関で特徴を比較するとわかりやすいでしょう。
各ローンの特徴を理解し、事業でのニーズに最適な融資を選択することが、よりよい資金調達への第一歩です。
急ぎの資金調達なら消費者金融が最適
消費者金融のビジネスローンは、即日融資に対応していることが多く、とにかく大急ぎで資金を調達する必要があるときに最適です。
カードローンも取り扱っている、プロミス、アコム、アイフル等がビジネスローンも展開しています。
プロミス 自営者カードローンは繰り返し利用可
・金利:6.3%~17.8%
・限度額:300万円まで
プロミス自営者カードローンは、即日融資も可能な、事業資金、プライベート資金に使えるローンです。
限度額の範囲内なら、カードローンとして何度でも繰り返し融資を受けられるので、急な資金調達のための借入枠として持っておくと安心でしょう。
アコム ビジネスサポートローンは個人事業主向け
・金利:12.0%~18.0%
・限度額:300万円まで
アコムビジネスサポートローンは、年収3分の1を超えた借入も可能なカードローンです。
個人事業主の方なら、アコムのカードローンからビジネスサポートローンへの切り替えもできます。
即日融資も可能なので、急にお金が必要になった時にも頼れるローンとなってくれるでしょう。
アイフルの事業サポートプランは担保/無担保の2種類
無担保ローン
・金利:3.0%~18.0%
・限度額:1万円~500万円
不動産担保ローン
・金利:3.0%~12.0%
・限度額:100万円~1億円
アイフルの事業サポートプランは、不動産担保ローンと無担保ローンがあります。
いずれも最短翌日に審査結果がわかりますので、急ぎの資金としての利用によいでしょう。
ただし事業サポートプランは創業前は申し込み不可で、創業後に申し込む場合も確定申告を行っている必要があります。
銀行が取り扱うビジネスローン
銀行のビジネスローンも個人事業主向けや、法人向けのものがあります。
金利は高めで、銀行カードローンと最高金利が近いものが多いです。
ただし、融資を受けられる額は消費者金融より大きめの設定ですから、必要に応じて利用するとよいでしょう。
PayPay銀行のビジネスローンはスマホで手軽に申し込み可能
・金利:1.8%~13.8%
・限度額:1,000万円
PayPay銀行のビジネスローンは、事業資金であればお金の使いみちは自由に決められます。
提出書類の少なさや、スマホで手軽に申し込める点が便利で、開業して間もない方も申し込めます。
GMOあおぞらネット銀行 融資(利用)枠型ビジネスローンあんしんワイドは繰り返し利用できる
・金利:0.9%~14.0%
・限度額:最大1,000万円
創業初年度から利用できるGMOあおぞらネット銀行のビジネスローンは、繰り返し借入と返済ができます。
オンライン完結型ですので、来店や決算書の提出も不要です。
信販会社のビジネスローンは特徴を把握しよう
信販系のビジネスローンとは、いわゆるカード会社等が取り扱うビジネスローンになります。
審査日数は消費者金融のように即日融資も可能な信販会社のビジネスローンが登場し、数日で融資も可能になるものが多いです。
ただし、限度額があまり大きくなく金利も消費者金融のビジネスローンと違いがないものも見つかります。
申し込み先はしっかり比較しておく必要があるでしょう。
オリックス・クレジット VIPローンカード BUSINESS
・金利6.0%~17.8%
・限度額:最高500万円
オリックス・クレジットの「VIPローンカード BUSINESS」は、法人経営者や個人事業主向けのビジネスローンです。
お金のつかいみちとしては、運転資金やつなぎ資金、納税資金などに適しています。またプライベートにも使えて安心です。
オリコ CREST for Biz(クレスト フォービズ) 個人事業主専用ローンカード
・金利:6.0%~18.0%
・限度額:10万円~300万円
CREST for Bizは、個人事業主の方のみ申し込めるローンカードです。
事業に関する使いみちに限定されており、ローンカードですから必要に応じて何度でも借入できます。
ATMだけでなく、インターネットや電話での借入もできるので、利便性が高いですね。
ビジネスローンの審査基準3点

ビジネスローンを受けるためには、発行している金融機関やローン会社、消費者金融等の審査を通過する必要があります。
審査基準は、公的機関の融資に比較すると甘いと言われていますが、もちろん誰でも審査に通るわけではありません。
申し込むローンにもよりますが、提出する書類も少なく、オンラインで完結するものがたくさん登場しています。
最適なビジネスローン選びが、使いやすさに直結するでしょう。
業績・財務状況は審査において重要
事業の業績や財務状況は、ビジネスローン審査においてももちろん重視されるポイントです。
ビジネスローンは、創業前に申し込めるものは多くなく、一定期間の事業の実績がある方が利用できるものです。
事業の状況がわかる決算書や確定申告書の提出によって、業績や財務状況を把握できるものですから、必要に応じてきちんと提出しましょう。
お金の使いみち
資金使途は、お金を貸し付ける側には重要な事項になります。
ビジネスローンでは、マイカーローンや住宅ローンのように、何を購入したのかがわかる名称ではありません。
しかし審査では資金使途は必ず申告するものです。きちんと答えられるように計画を立てておきましょう。
返済能力があるかどうか
ビジネスローンでの返済能力の判断は、審査によって行います。
入ってくるお金に見合った借入になっているか、これまでのローン履歴等の信用情報に問題がないかを審査でチェックしていきます。
創業後に申し込むローンが大半ですから、申し込むまでの経営の状態をきちんと振り返っておきましょう。
ビジネスローンのメリット・デメリット
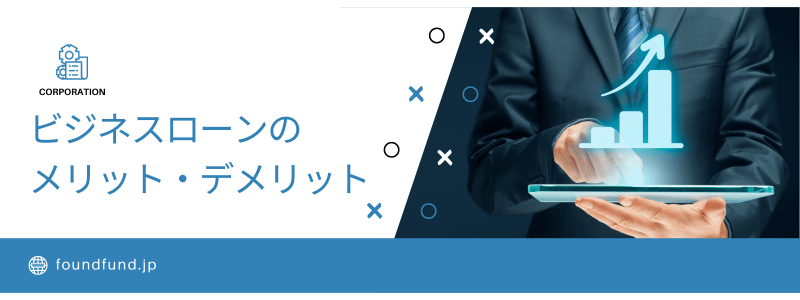
ビジネスローンには、事業の成長や拡大を支援するメリットがある一方で、返済負担や融資条件の厳しさといったデメリットも存在します。これらを理解し、賢く利用することが事業成功の鍵です。
ビジネスローンの3つのメリット
ビジネスローンのメリットには、総量規制の対象外である点と審査スピードがまずあげられるでしょう。
総量規制対象外のローンとなる
ビジネスローンは総量規制の対象外です。
貸金業法で定められた総量規制は、年収の3分の1を超えた借り入れはできない法律ですが、ビジネスローンは対象になりません。
事業者が個人名で利用する場合にも、ビジネスローンなら審査を通過すれば年収の3分の1を超えても融資を受けられます。
審査にかかる時間が短い
公的な融資や銀行のローンに比較すると、ビジネスローンは審査にかかる時間が短く、融資まで大変スピーディーです。
銀行や公的機関なら2週間から1ヶ月以上かかることもある融資が、ビジネスローンなら最短即日~1週間、長くても10日程度で受けられるようになります。
担保や保証人なしで申し込めるビジネスローンも多い
担保や保証人は、銀行や公的機関の融資では必要となるケースが多いのですが、ビジネスローンでは無担保・無保証人で申し込めるものが大半を占めます。
ただし、融資を受ける金額や審査状況によって、担保や保証人が必要になる場合もあるため、ビジネスローンのスペック等をきちんと確かめておきましょう。
ビジネスローンのデメリット
ビジネスローンは、事業者の方も利用しやすいメリットが豊富な一方で、デメリットも存在しています。どのようなデメリットがあるのでしょうか。
公的機関や銀行に比較して金利が高め
ビジネスローンは、日本政策金融公庫や銀行等の創業融資に比較するとかなり金利が高いものがあります。
日本政策金融公庫ならどれほど金利が高くても3%台、銀行も2%台の融資となっていますが、ビジネスローンは最高金利が18.0%のものもあります。
金利に大きな差があるので、利用日数や利用額には十分な注意が必要です。
融資を受けられる額は低め
審査によりますが、公的機関が数千万円、銀行なら数千万円~1億円の融資も可能であるのに比べると、ビジネスローンは最高でも数百万円程度の融資額です。
お金の使いみちによっては、ビジネスローンでも十分な場合もありますが、設備資金などであればまったく適していないといえるでしょう。
利用目的に応じたローンの選択が重要になります。
銀行融資等の審査に影響を与えることがある
ビジネスローンを法人で利用すると、決算書に借入先を記載する必要が出てきます。
決算書にビジネスローンを利用したことが明記してある状態で、銀行や公的な金融公庫から融資を受ける場合には審査に影響する可能性もあります。
創業融資とビジネスローンは目的に応じて利用しよう
これから事業を開始する方にとって、融資には不安を伴うことがありますが、きちんと特徴を知っておけば過剰に心配する必要はありません。
創業融資では、公的機関などの低金利のものを基本として、緊急時等にビジネスローンを適宜利用する方法が理想的です。
いずれにしても、資金調達の方法をたくさん知っているほど、適切なものを選べるでしょう。事業計画を立てる際に、必要に応じて創業融資、地方自治体による融資、ビジネスローン等を検討するとよいですね。